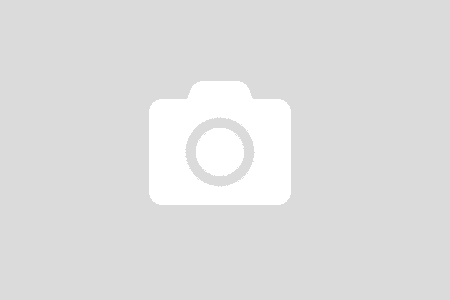ディスカッション
処方H1抗ヒスタミン使用とリスクの増加との関係が見つかりました18歳以上の米国成人における肥満の割合。年齢および性別を一致させた対照と比較。処方H1抗ヒスタミン薬の使用者は、体重、BMI、胴囲、インスリンレベルが有意に高かった。
強力なH1拮抗作用を持つ非定型抗精神病薬は、体重増加と強く相関している。オランザピンなどの高い抗ヒスタミン作用を持つ新世代の抗精神病薬は、体重増加を引き起こします(8)。ただし、現在の分析では、非定型抗精神病薬を除外し、アレルギー緩和のために処方されたH1抗ヒスタミン薬に焦点を当てています。以前の研究(9)は、子供と青年のNHANES 2005–2006データセットを使用して、肥満とアレルギー症状との関連を発見しましたが、成人におけるこの関係や処方H1抗ヒスタミン使用の影響については調査していません。処方H1抗ヒスタミン薬で観察された体重増加の考えられる理由のひとつは、それらの使用に伴う鎮静作用の増加によるものかもしれません。この分析で処方された第2世代のH1抗ヒスタミン薬は鎮静作用がないと見なされますが、これは他の要因によって軽減される可能性があります。サンプルで最も一般的に処方されているH1抗ヒスタミン薬であるセチリジンは、古い鎮静作用のある抗ヒスタミン薬であるヒドロキシジンの活性代謝物であるため、鎮静作用はまだわずかです(10)。第二に、これらの薬剤は処方された投与量では鎮静作用がないと見なされますが、これらのH1抗ヒスタミン薬の投与量と使用法は、NHANES 2005–2006データセットでは利用できませんでした。処方H1抗ヒスタミン使用は、エネルギー消費と体重増加の減少をもたらす鎮静作用をもたらした可能性があります。
処方H1抗ヒスタミン使用は、年齢と性別を一致させた対照と比較して、より高い胴囲とインスリン濃度にも関連していました。 。中心性肥満は、インスリンレベルとインスリン抵抗性の増加と高度に関連しています(11)。さらに、腰囲の上昇は、糖尿病や心血管疾患のリスクを高める一連の障害であるメタボリックシンドロームの基準の1つです。ヒスタミンがインスリン機能とエネルギー消費を調節するメカニズムは完全には解明されていません(12)。ヒスタミンはラットのグルコース取り込みを促進しましたが、ヒト脂肪細胞は促進しませんでした(13)。ヒトでは、インスリンがH1受容体の発現をアップレギュレートすることが示されています(14)。 H1受容体の発現は、インスリンレベルが上昇すると上昇するレプチンレベルによっても調節されます(15)。 2005〜 2006年のNHANESはレプチンレベルを測定しませんでした。おそらく、処方H1抗ヒスタミン薬の使用で観察された体重は、H1受容体の発現と結合の破壊に関連しており、インスリンとレプチンのシグナル伝達の障害につながります。エネルギー代謝におけるヒスタミンの役割の程度を判断するには、さらに研究が必要です。
処方H1抗ヒスタミン薬使用者の太りすぎのORは1.55でした。この研究で計算されたORは、実際の相対リスクを過大評価する傾向がありますが、価値のある概算を提供します。アメリカ人の3分の2は太りすぎまたは肥満であるため、体重増加に関連する要因をさらに調査することが重要です。
この性質の分析にはいくつかの制限があります。まず、男性の2倍の女性を対象に分析を行いました。限られたサンプルによると、処方H1抗ヒスタミン薬の使用と肥満との関連は、女性よりも男性の方が強いように思われるため、この違いを調査するためにさらに調査を行う必要があります。次に、2005〜 2006年のNHANESデータセットは、処方薬の使用のみを報告します。いくつかのH1抗ヒスタミン薬は処方箋なしで入手できるため、H1抗ヒスタミン薬を服用しているサンプルの実際の個人数は不明です。米国では推定50人がアレルギーに苦しんでおり、そのうちの約35〜50%が市販の抗ヒスタミン薬を使用しているため、この分析では抗ヒスタミン薬の影響を過小評価している可能性があります。 H1抗ヒスタミン薬はますます入手しやすくなっているため、体重増加とメタボリックシンドロームの発症の増加に寄与している可能性があります。因果関係は、この横断的分析のみに基づいて処方H1抗ヒスタミン薬の使用に起因するものではありませんが、抗ヒスタミン薬の使用の増加、肥満、および根本的な危険因子の関係を調査することが不可欠です。